特養で働くとき、ネットや大手ブログでは「アセスメント能力が伸びる」「手技が衰える」「一人の利用者と長くかかわれます」など、表面的な情報ばかりが目立ちます。実際はルーティン作業が多くアセスメント能力なんて伸びません。手技もやるときはやるし、採血とかの主義なんてすぐ勘が戻ります。一人の利用者と長くかかわれますが、そもそも特養なので認知症の人ばっかりです。
本当に大事なのは「働く側が得できるか、ラクできるか、お金になるか」という現実的なポイント。このブログでは、ネットに載っていない損しない特養の選び方を、あなた目線で本音でまとめます。
看護師が特養を選ぶとき本当に見るべきポイント
求人やネット情報では見えない、現場で本当に差がつく8つのチェックポイントはこれです。
- オンコールの中身と呼び出し理由(特に吸引の有無と介護士の資格)
- 介護業務の範囲とグレーゾーン
- 看護師の配置バランス(正看・准看の割合、年齢層、役職チャンス)
- 処遇改善手当が看護師にどれくらい支給されるか
- 有給やシフトの融通が利くか(1日あたりの看護師人数も要確認)
- 看護記録やICT化の進み具合
- 看護師の雇用形態(常勤/パート/派遣の割合)
- 看護師の在籍年数や離職率(離職率が高い=昇進チャンスの側面も)
オンコールの中身と呼び出し理由(特に吸引の有無と介護士の資格)
特養は「夜勤なし・オンコールあり」が基本ですが、呼び出しの理由や回数は施設で全く違います。
中でも「吸引対応」が多いと、夜間でも頻繁に呼ばれるのでプライベートが削られやすいです。
- 吸引利用者が何人いるか(そもそも受け入れをしているのか)
- 実際どんなタイミングで看護師が呼ばれるのか
介護士の吸引資格について
介護士でも、「認定特定行為業務従事者(例:たん吸引等研修修了者)」という国の認定資格を持っていれば、
一定の条件下で吸引(口腔・鼻腔吸引、胃ろうの管理など)や経管栄養が可能です。
この資格を持った介護士がいれば、夜間も状況に応じて介護士が吸引対応できるため、看護師が毎回オンコールで呼ばれる必要はありません。逆に資格保有者がいなければ、「吸引が必要=ほぼ毎回看護師出動」になるので、負担が全く違います。
介護業務の範囲
「看護師は介護業務なし」と書いてあっても、実際にはグレーゾーンが山ほど。全部面接で細かく聞くのは現実的じゃないですが、自分が絶対やりたくないことや不安な業務だけでも事前に確認しておくのがおすすめ。
例として
- オムツ交換・入浴介助
- 普段は介護士だが、急ぎやトラブル時に看護師もやることがあるか
- ナースコール対応
- 看護師もでる場合はあるのか
- 移乗・食事介助
- どこまで巻き込まれるのか
このあたりを「差し支えなければ…」と聞いてみるだけでも、入職後のミスマッチを減らせます。
看護師の配置バランス(正看・准看の割合、年齢層)
昇進や役職は基本的に正看が有利。若い正看が少ない施設は「早く役職につける穴場」にもなります。
私はお金が重要だったので役職も狙い、面接の際にも割合と年齢層は重視しました。
ただし、手当と忙しさが見合うかは実際働かないとわからない。
とはいえ、履歴書で「人を束ねた経験」は転職や年収交渉で非常に強みになります。看護師の場合(今の時代?)、人の上に立つことに対して非常にネガティブな意見を持っている人が多いと思いますが、チャンスがあるならば絶対にチャレンジしてみるべきだと思います。
面接では「正看・准看の割合はどんな感じですか?」「特養は年齢層が高いイメージがありますが、ここの年齢層はどれくらいなんでしょうか?」と聞けば自然です。
看護師の役職について
特養というよりは、高齢者施設の役職=言い換えればキャリアアップの話ですが、イメージがわかないと思うのでザックリ説明します。以下のような点を確認すればいいかと思いますが、どこかのタイミングでまた別記事でまとめます。
- 看護師が役職についている割合
- 特に看護部門以外の部門で看護師が役職についているか
- 法人内で、看護師として働くうえでキャリアの天井や上位職があるか
- 病院に置き換えてみると、病棟内で師長までは用意されているが、例えば看護師でも薬剤部のトップに立てるかどうかみたいな話
- 複数事業所を運営している法人なら、それらを統括するエリアマネージャーのようなものがあるか
- そこには看護師の立場でもなれるのか、もしくは介護士や社会福祉士しかなれないのか、それともそれ専用の総合職のような立場でないと慣れないのか
お金の面でもそうですが、今後の自分の将来性・キャリアを考えたときに、履歴書に書ける人を束ねた経験は有利なのですが、法人ごとにキャリアアップの方向性は違います。基本的に特養は介護施設になるため、介護士のキャリアアップには積極的な反面、看護師は病院ほど力を入れられていないのも事実、法人規模・構造も含めて確認しておきましょう。
処遇改善手当が看護師にどれくらい支給されるか
処遇改善手当は本来介護士の給与アップ目的。施設によっては看護師に全く配らない所も普通にある。逆に全員均等や一部だけ支給する所もあり、ここは年収に直結するので確認したいところ。
とはいっても看護師を集めるために、看護師に支給しているところはアピールのため大体求人票に書いてあると思います。
知らずに入職すると「思ったより手取りが低い」で大損します。
有給やシフトの融通が利くか(1日あたりの看護師人数も要確認)
有給取得や急な休みが取りやすいかは超重要。特に1日あたり何人で現場を回しているかが大きなポイント。
人数が少ないとシフトもガチガチになりがちなので、「普段は何人で勤務していますか?」と聞いておくと後悔しません。
看護記録やICT化の進み具合
私は手書きのような非効率な働き方が絶対に嫌だったので、手書きメインの施設は最初から選択肢に入れませんでした。最近は一人一台iPhoneを持って業務するようなICT先進施設も増えています。
本当にラクなのは「電子カルテ×パソコン入力」。でもあまりないと思います。
「紙カルテ」でも普段の記録がパソコンならOK。逆に「電子カルテなのに記録は紙で手書き」みたいなアホ見たいなところもある可能性があります。
- 同じ内容の記録を3冊(看護記録・介護記録・申し送りノートなど)手書きで書かされる
- 日々のバイタルや処置を全部バラバラの紙に転記
- 記録ミスや抜け漏れにはいちいち訂正印が必要
これ等は手書きの弊害です。こうした無駄を抱えた施設は本当にストレスです。
面接・見学では「普段の記録はパソコン入力ですか?手書きですか?」と聞くと一発でわかります。
看護師の雇用形態(常勤/パート/派遣の割合)
常勤・パート・派遣のバランスが悪いと、常勤にオンコールやシフト負担が集中します。「パートさん・派遣さんの割合は?」と聞くだけで雰囲気がつかめます。
看護師の在籍年数や離職率(離職率が高い=昇進チャンスの側面も)
「長く勤めている看護師が多いですか?」「離職率はどうですか?」とサラッと聞けるなら聞くのもありです。離職率が高い職場は人間関係や業務量のリスクもありますが、逆に“回転が速い=若手でも早く昇進できる”チャンスが転がっている場合も。入ってみると意外と悪くないパターンもあるので、「離職率高い=100%地雷」とは限らないことも頭に入れておくと損しません。
まとめ
求人やネットの表面的な情報を真に受けて選ぶと、あとで損をするのは自分自身。ここで挙げた8つのリアルなポイントを面接や見学でしっかり確認し、自分の目で現場を見て選んでください。「なんとなく」や「イメージ」だけで決めず、実利で後悔しない選択を!
「これだけ色々聞いたら面接で落とされるんじゃ…」「施設長に嫌な顔されるのでは?」と不安に思う人もいるかもしれません。でも、普通の社会人としての礼儀・配慮をもって質問したのに、嫌な顔をされたり、失礼な対応をされたなら――その時点でその施設は選ぶ価値なしです。
(実際、特養は施設長の人柄で雰囲気が大きく左右される傾向があります)
それに、仮にあなたが60代の看護師であるなら話は別ですが、特養も慢性的に看護師不足。
若い看護師というだけで重宝される時代です。限度はありますが、必要なことは“多少上から目線”くらいでも大丈夫な面すらあります(もちろん言い方には注意)。
むしろ、それくらい「自分で条件を選ぶ」意識を持って働き方を決めてほしい。
というのが現場で働いた身からの本音です。
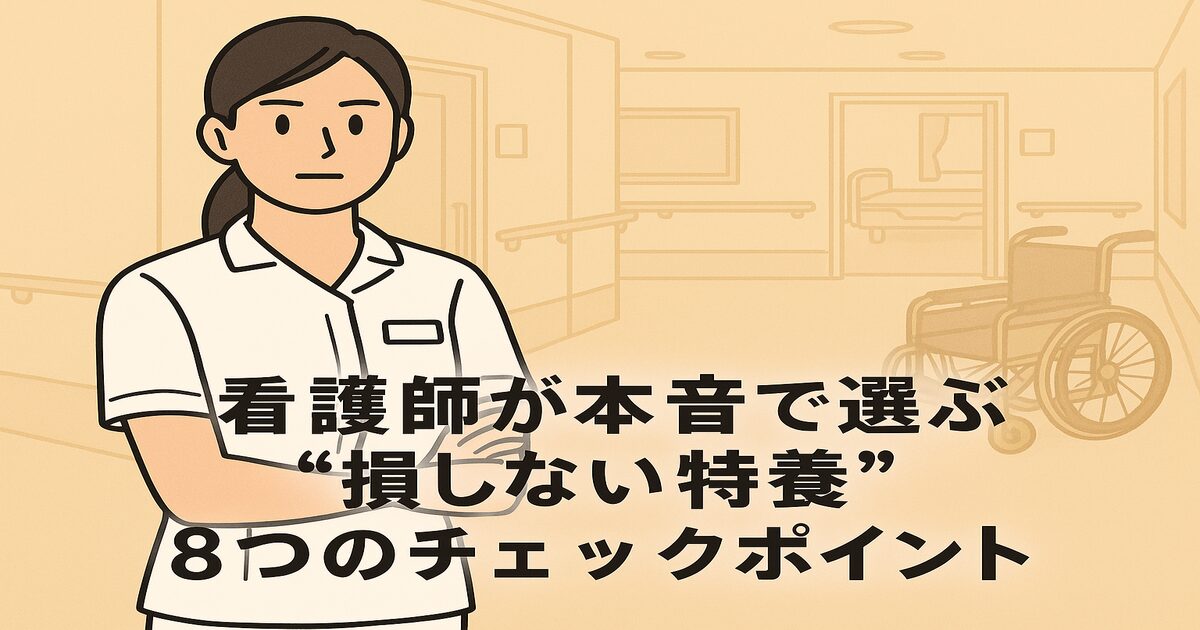

コメント