「安定した仕事」って本当に正解なのか?
「看護師=安定した仕事」というイメージは、世間でも根強いものがあります。求人サイトやキャリアガイドを見ると、「手に職」「一生食いっぱぐれない」といった言葉が並びます。
親世代からも「看護師なら将来安心」と言われ、進路を決めるときの大きな後押しにもなりやすい仕事です。
たしかに、医療や介護の現場は慢性的な人手不足で、景気に関係なく求人が出ています。リストラや倒産で職を失うリスクが少ない点は、他の多くの職種と比べても圧倒的に“安定”していると言えるでしょう。
しかし、実際に現場で何年も働き続けていると、単純な“安定=正解”では片付けられない現実が見えてきます。
例えば、安定の裏には「忙しさやストレス」「体力的な限界」「キャリアの行き詰まり」といった悩みが付きまといます。また、生活や価値観が変化する中で、「本当にこのままでいいのか?」と疑問が湧いてくる人も多いはずです。
“安定しているから幸せ”とは限らない。現場で働き続けていると、そう実感する瞬間が必ずやってきます。
現場ごとに違う「安定」のカタチ
一口に「看護師の安定」といっても、実はどの現場で働くかによって、その意味や感じ方は大きく変わります。
「大病院」「特養・介護施設」「クリニック」「訪問看護」など、それぞれの職場ごとに“安定”の中身が違うのです。
大病院の「安定」
大病院は、組織力・規模ともに大きく、「雇用の安定感」や「福利厚生」「研修制度」などのバックアップが充実しています。
収入面でも夜勤や手当がしっかりしており、社会的な肩書きも得やすい。特に若いうちは最先端の医療技術に触れられる機会も多く、経験やキャリアアップにつながりやすいのが特徴です。
一方で、現場は常に忙しく、シフトや人間関係のストレスも大きい。「安定=働きやすさ」ではなく、「組織の歯車としての安定感」になりやすい側面もあります。また、実力主義の世界で生き残るには、ある程度の覚悟や自己管理能力も必要です。
●特養・介護施設の「安定」
特養や介護施設は、急性期病院ほどの忙しさは少なく、残業や夜勤が減りやすい反面、給与やキャリアアップの幅は狭くなりがちです。その代わり、「地元で長く働き続けたい」「生活リズムを大切にしたい」という人には、安定した職場となります。
利用者さんと長く関われる、人間関係が密になりやすいなど、“地域の一員としての安定感”や“日々の小さな変化”を感じやすいのが特徴ですただし、看護師の人数が少ない分、一人ひとりの責任や負担が大きくなる場合もあり、施設ごとに「安定」の質はかなり異なります。
クリニック・訪問看護の「安定」
クリニックは基本的に日勤のみ、土日休みのところも多く、「家庭やプライベート重視」の安定感が得やすい職場です。しかし、経営者(院長)や患者数によって雇用の安定度が左右されやすく、スタッフの入れ替わりが激しい場合も。
特に男性の場合、クリニックは採用自体が少なく、“働き口として実質選択肢から外れることが多い”のも現実です。
クリニックの求人は圧倒的に女性を前提としていることが多く、男性看護師は最初から応募対象にならないことも珍しくありません。もちろん求人票に女性だけのような書かれ方はしませんが。
訪問看護は自由度が高く、利用者宅に直接伺う形のため「自分のペースで働きやすい」「独立した働き方ができる」といった安定感が得られる一方で、緊急対応や夜間出動など不安定な要素もつきまといます。地域や事業所によって収入や働きやすさの差が激しいため、職場選びにはより慎重さが求められます。
“安定”の裏にある「将来不安」
「安定した仕事」と言われる看護師ですが、現場に身を置くほど“将来不安”を感じることが増えてきます。
とくに「今の職場にこのままずっといられるのか?」「歳を重ねたときにも働き続けられるのか?」という漠然とした不安は、誰しも一度は抱える悩みです。
体力勝負の現場で、年齢を重ねても働き続けられるのか?
看護の仕事はとにかく体力勝負。若いうちは残業や夜勤も体力で乗り切れてしまう部分がありますが、年齢を重ねるごとに「身体の衰え」や「気力の限界」を感じる場面が増えていきます。
【男性の場合】
男性看護師の場合、40代・50代・60代と歳を取っても今のまま現場で働き続けられるのか、という悩みはとても切実です。大病院など病棟の最前線で“おじさん・おじいちゃん看護師”として仕事を続ける現実を想像したとき、「実際に体力がもつのか」「若いスタッフと同じように動けるのか」という心配がつきまといます。
また、昇進や管理職のポジションを目指すにも、現場には優秀な同世代・先輩たちが残り続けているため、「管理職に上がれる保証なんてどこにもない」という焦りも感じます。
年齢を重ねた男性看護師に対する職場の目線は、時にシビアです。
「若い頃は力仕事や夜勤で頼りにされたが、年齢を重ねるごとに“どんな立ち位置で現場にいればいいのか”が見えにくくなった」という声も多いです。
さらに、クリニックなどの選択肢が男性看護師にはほとんど開かれていないという厳しい現実もあります。
多くのクリニックでは女性看護師の採用が前提で、「体力がもたなくなったらクリニックでのんびり働く」という選択肢は、実質ほぼ用意されていません。
【女性の場合】
女性看護師の場合は、妊娠・出産・育児など、ライフイベントによる“働き方の揺れ”が男性より圧倒的に多いのが現実です。
産休・育休を取っても、復帰後に「現場のスピードや業務量についていけるか」「夜勤や急変対応を再び担えるのか」と不安になる人が大半です。
また、子育て中や家庭の事情(パートナーの転勤、親の介護など)で夜勤やフルタイム勤務が難しくなり、「自分のキャリアをこの先どう描いていけばいいのか」と悩む場面も増えます。
現場では「子育てママ=戦力ダウン」とみなされる空気が残るところもあり、肩身の狭さや働きにくさを感じることも。
さらに、管理職やリーダー職を目指したくても「家庭と両立しながら役職を担うのは大変そう」と不安を感じている女性も多いです。プライベートとの両立、ワークライフバランスの維持――理想と現実のギャップに悩む女性看護師は決して少なくありません。
【その他の現実的な不安】
- 看護・介護業界そのものが高齢化・少子化やAI導入などで大きく変化しつつあり、「今のスキルや経験だけでこの先も生き残れるのか?」という漠然とした不安
- 自分が「安定」を手に入れたつもりでも、業界・社会全体が変わればそれが保証されなくなる現実
どんなに“安定”だと言われていても、現場で働き続けているからこそ見えてくる不安や、将来への迷いはなくなりません。
働き続けて気づいた「安定」より大事なもの
実際に現場で何年も働く中で、「安定」よりももっと大事なものがあることに気づく瞬間が何度もありました。
例えば、どれだけ安定した職場でも、家族との時間や自分の健康・プライベートを犠牲にしてまで続けたい仕事なのか。
これは、年齢を重ねるほど切実なテーマになります。
夜勤明けに寝不足で家に帰っても、家族との会話もままならない。「家に帰っても休めない」「土日も出勤で子どもの行事に参加できない」…こういった悩みは多くの看護師がぶつかる現実です。
また、精神的な余裕や自分らしさを保つことも大切です。忙しさや人間関係のストレスが続くと、どんなに“安定”していても心身ともに疲れ果ててしまい、「自分はこのままでいいのか?」と自問するようになります。
そして、「安定」という言葉に縛られすぎると、新しい挑戦や可能性を自分から狭めてしまう危険もあります。
「今のままが安定だから…」と現状にしがみつくより、自分の価値観や大切にしたいものを見つめ直すことで、仕事も人生ももっと豊かにできるはずです。
「安定」を求めすぎないために
今は「安定した仕事」にこだわらなくても、人生の途中でやり直すことが当たり前の時代です。
実際、看護師としてもキャリアチェンジや働き方の多様化が進み、「一つの現場に縛られずに生きる」ことができるようになってきました。
- 「正社員」や「夜勤あり」にこだわらず、自分のペースでできる働き方を模索する
- いろいろな現場を経験してみることで、自分に合った「安定感」を見つける
- 転職や失敗を恐れず、自分の気持ちに素直になる
大事なのは「安定」を目的にすることではなく、「自分にとっての安定」を見つけることだと思います。
選択肢を広げること・失敗してもやり直せることを知っておくことで、長い人生をもっと柔軟に歩んでいけるはずです。
まとめ──自分にとっての「安定」とは
看護師の「安定」という言葉はとても強く響きますが、実際“自分にとっての安定”は人によって全く違います。
- 給料が毎月入ることが「安定」なのか
- 家族との時間や健康を守れることが「安定」なのか
- キャリアアップや成長の機会があることが「安定」なのか
それぞれの「安定観」をしっかり考えることで、後悔のない選択ができるはずです。
「安定した仕事」を目指すのは悪いことではありません。
でも、その“安定”の中身を自分なりにしっかり見つめ直すこと。
これからの時代は、そんな“自分基準の安定”を意識して働き方を選ぶことが、もっと大切になってくるのではないかと思います。
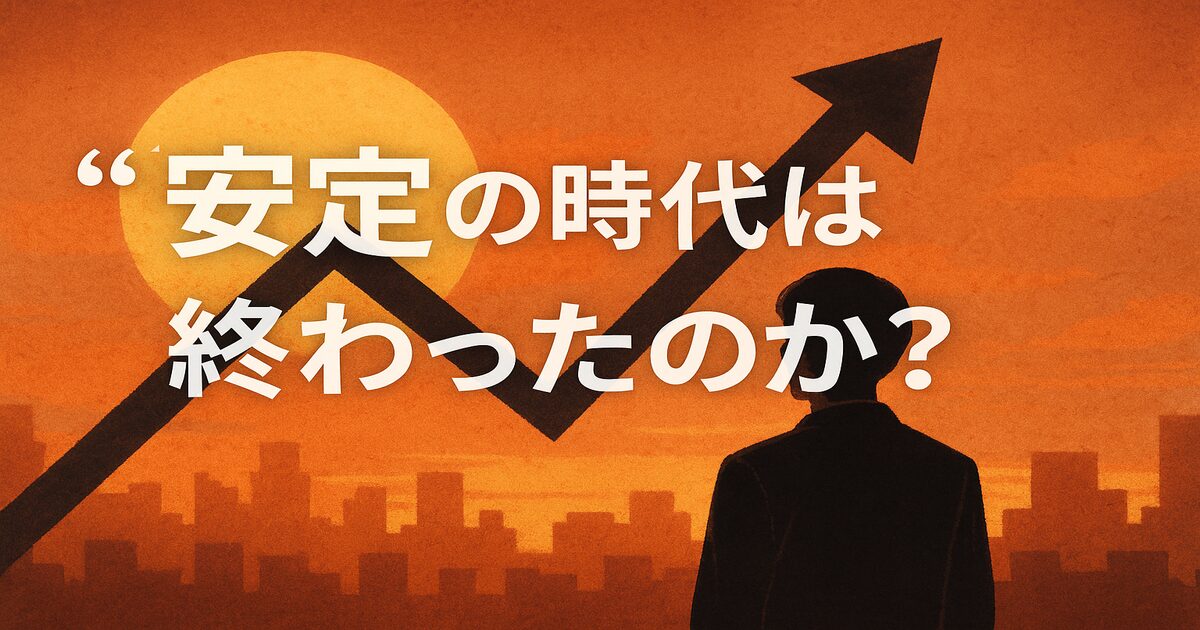


コメント