65歳の壁とは?
- 基本的な意味
- 障害福祉サービス(障害のある人の生活支援を公費で行う仕組み)を利用している人が65歳になると、介護保険(保険料と税金で運営される高齢者向けサービス)を優先して使うよう求められるルールです。
- なぜ「壁」と呼ばれるか
- それまで使っていたサービスや負担の仕組みが65歳を境に変わり、利用者の生活や財政に大きな影響を与えるため、心理的・制度的な障壁として捉えられています。
65歳の壁が生まれた理由
- 社会保険優先という考え方
- 日本の社会保障には「社会保険優先の原則」があり、似たサービスが税方式(公費)と保険方式(保険料)で存在する場合は保険方式を優先する決まりです。介護保険は保険方式、障害福祉サービスは税方式なので、65歳になったら原則として介護保険を使うよう定められています。
- 財源構造の違い
- 障害福祉サービスは国や自治体の税金を財源とするため利用者負担が低く抑えられています。一方、介護保険は利用者と保険料を払う人たちの連帯によって支えられるので、保険の仕組みを優先することで公費支出を抑える意図があります。
- 制度改正の経緯
- 介護保険は2000年に始まり、障害者総合支援法は2013年に施行されました。制度創設当初から両者は別立てで運営され、65歳で切り替えが生じる構造になっています。その後、2017年には65歳になっても同じ事業所を利用し続けられるよう介護保険と障害福祉サービスの一部を相互乗り入れした「共生型サービス」が導入されました。
制度改正の背景と共生型サービス
- 共生型サービスの狙い
- 介護保険と障害福祉サービスの双方を提供しやすくするために指定基準を緩和し、同じ事業所で両方のサービスを受けられるようにした制度です。
- メリット
- 65歳を過ぎても慣れた事業所を継続利用できる
- 利用者の選択肢が増える
- 地域の事情に合わせた柔軟な支援が可能になる
- 普及の課題
- 実際には共生型の指定を受けている事業所はごく少ない。令和4年11月時点で、通所介護4万3,226事業所のうち生活介護140か所、自立訓練8か所、放課後等デイサービス3か所しか共生型の請求をしていません。介護保険事業者が障害福祉サービスに不慣れであることや書類負担の違いなどが理由として挙げられます。
65歳で変わる自己負担
障害福祉サービスの負担 (H3)
- 応能負担
- 所得に応じた上限額があり、生活保護や市町村民税非課税世帯なら自己負担は0円、「一般1」は月9,300円、「一般2」は月37,200円が上限です。
- 世帯の考え方
- 本人と配偶者の収入のみで判断するため、同居の親や子の収入は考慮されません。この仕組みのため、実際には0円負担に該当する利用者が多いという現場感覚があります。
介護保険サービスの負担
- 応益負担
- サービス利用料の1割が基本で、所得が一定額を超えると2割や3割になります。
- 高額介護サービス
- 介護保険の自己負担が月44,400円を超えると超過分が戻ってくる制度がありますが、低所得者でも1割負担がかかるため65歳になると負担増となることが多い。
- 負担のギャップ
- 障害福祉では0円~3万7,200円の範囲で抑えられるのに対し、介護保険では利用量や所得に応じて費用が跳ね上がる可能性があります。
自己負担の軽減策
- 自治体独自の助成
- 介護保険に移行した後も負担を抑えるために、自治体が独自に補助を行う場合があります。
- 国による負担軽減
- 制度改正で低所得者に対する新たな負担軽減策が検討されており、将来的には負担が緩和される可能性があります。
サービス内容の違い
- 障害福祉サービス
- 移動支援(外出介助)、行動援護(認知や精神障害がある人への支援)、就労支援など障害特性に合わせた多様なメニューがあります。3時間以上の長時間サービスや社会参加を促すプログラムが認められている点が特徴です。
- 介護保険サービス
- 入浴や排せつ介助などの身体介護、掃除や洗濯などの生活援助が中心。家族が同居している場合は生活援助時間が短く限定されるなど細かな基準があり、「ヘルパーは粗大ごみの処理はできない」など行える内容が細かく定められています。
- 変化による影響
- 障害福祉サービスで長時間介助に慣れている利用者が、介護保険に移行すると細切れのサービスに変わり、生活リズムが乱れやすいといった声があります。
現場で起きている課題
多くの利用者が0円負担
- 障害福祉サービスでは負担が0円または少額で済む人が多く、65歳になると突然1割負担が発生することに戸惑いや不安の声が上がります。支援者は事前に負担の変化を説明し、移行後の家計の試算などを行うと良いでしょう。
共生型サービスの利用難
- 制度はあるものの実施事業所が少なく、利用者が共生型サービスを選びたくても地域に選択肢がない場合が多い。
- 事業者側では、障害福祉の経験がないことによる不安や、書類作成の煩雑さが参入を阻む要因となっています。
行政判断によるばらつき
- 障害者総合支援法では、介護保険に同等のサービスがない場合や介護保険だけでは不足する場合には上乗せ利用を認めることとしています。例えば、移動支援や行動援護など介護保険に相当するサービスがない場合は65歳を過ぎてもそのまま利用できます。
- しかし市町村によっては「要介護度4以上の人しか上乗せ利用を認めない」「支援区分5以上の人に限定する」など独自の基準で制限を設ける例があり、これらは違法と指摘されています。支援者は自治体の内規を確認し、適切な運用を求める必要があります。
裁判や最近の動き
岡山市事件
2018年、岡山市が65歳を迎えた障害者の福祉サービスを打ち切った処分を巡り、岡山地裁は市の処分を違法と判断し、介護保険と障害福祉サービスの併用が認められました。この判決以降、行政による一律打ち切りは慎重になっています。
千葉市事件と最高裁判決
千葉市の事例では、65歳になって介護保険申請を拒否した利用者への支援を打ち切ったことが争われました。2025年7月の最高裁第一小法廷は、二審判決を破棄し審理を東京高裁に差し戻しましたが、介護保険優先原則そのものは争点とせず、「介護保険利用により自己負担が生じることは法令上当然に予定されている」としました。今後の差戻し審では、要介護認定を経ずに障害福祉サービスを支給できるかどうかが焦点となります。
今後の制度改正
国は総合支援法改正で低所得者の負担軽減策を検討しており、また、65歳になっても従来の支援を続けられるよう制度を見直すべきとの意見も多く出ています。
支援者が押さえておきたいポイント
- 早期の情報提供
- 利用者が65歳になる前から制度の違いや負担の変化を説明し、家族や本人と一緒に移行後の生活を考えておきましょう。
- 特に金銭的な負担が生じるため、利用者にとってはかなりの反発が予想されます。
- 上乗せ利用の活用
- 介護保険に同等のサービスがない場合や不足する場合は、障害福祉サービスの継続利用や上乗せ利用が可能です。自治体によって運用が異なるので、相談支援専門員が積極的に申請や調整を行うことが重要です。
- 共生型サービスの普及に協力
- 地域で共生型サービスを提供する事業所を把握し、利用者が継続利用できるよう事業所と連携しましょう。また、新たに共生型サービス指定を受ける事業者へのサポートを行政に働きかけることも大切です。
- 最新情報の確認
- 裁判例や制度改正の動向を常にチェックし、利用者に誤解のない情報を提供してください。
- 所得区分と家族の範囲を説明
- 利用者負担の上限額は本人と配偶者の所得のみで決まること、障害福祉では0円負担が多いことをきちんと説明し、介護保険移行後の生活費をシミュレーションしましょう。
- 行政との連絡調整
- 最終的に障害福祉として65歳以降も利用できるかは行政判断になります。常日頃から行政との連絡を密に取り合い、自身の担当するエリアでの動向や他の判例等可能な限り情報を集めておきましょう。
まとめ
65歳の壁は、障害福祉サービスから介護保険への移行で生じる制度上のギャップです。社会保険優先の原則により税方式から保険方式へ切り替わるため、利用者負担が増え、サービス内容が変わるという現実があります。
障害福祉サービスでは所得に応じた上限額があり0~3万7,200円で抑えられますが、介護保険では1~3割負担が基本。共生型サービスや上乗せ利用といった仕組みで壁を低くする取り組みが進められているものの、事業所の少なさや自治体の運用差が課題です。
支援者は制度の背景と現状を理解し、利用者に寄り添ったプランニングと継続的なサポートを行うことが求められます。長期的には制度の統合や負担軽減の議論も進んでおり、最新情報を注視しながら、利用者が安心してサービスを受けられるよう支援していきましょう。


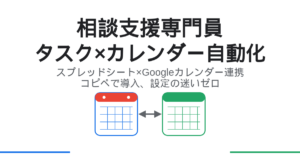

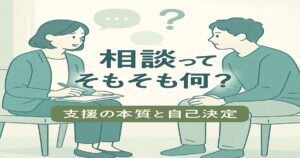



コメント