相談支援専門員とは?
相談支援専門員は、障がいのある方やそのご家族が地域で安心して暮らせるようにサポートする専門職です。イメージしやすく言えば「障がい分野のケアマネージャー(ケアマネ)」です。高齢者分野ではケアマネが介護サービスの計画や調整を担いますが、相談支援専門員は障害のある方や障害児、そのご家族を対象に、福祉サービスやさまざまな支援を橋渡しする役割を持っています。
障がい者の定義と対象
ここでいう「障がい者」とは、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)など、日常生活や社会参加にハードルを感じる方を指します。また、障害児(0歳から18歳未満の子ども)も対象です。
たとえば、3歳児健診で発達の遅れを指摘されたお子さんや、学校生活・進学・就労への不安があるご家庭なども、相談支援専門員のサポート範囲に含まれます。
相談支援専門員には、成人(高校卒業後)を中心に支援する人と、児童(高校卒業まで)を中心に支援する人がいます。制度上も「指定相談支援事業所」は成人と児童で分かれていることが多く、担当するケースや相談内容も異なります。
また、上記の身体・知的・精神など、それぞれ得意な分野や経験の少ない分野があるのも特徴です。一人ですべての年代・分野を担当する場合もあれば、「児童だけ」「成人だけ」と特定の分野に特化して支援する相談支援専門員もいます。
【成人担当(高校卒業後)】
たとえば――
- 統合失調症で自宅療養が続いている20代の方が、就労移行支援を利用してアルバイトにチャレンジしたい
- ADHDの診断がある若者が、一般就労が難しく、福祉的就労(就労継続支援B型など)を希望している
- うつ病で長く休職していた方が、社会復帰や一人暮らしを目指して生活訓練サービスを利用したい
【児童担当(高校卒業まで)】
たとえば――
- 自閉スペクトラム症(ASD)と診断された小学生が、放課後等デイサービスを利用して集団生活に慣れたい
- ADHDのある中学生が、学校や家庭での困りごとについて相談し、療育や学習サポートを受けたい
- 脳性まひで医療的ケアが必要な幼児が、保育園や学校生活を安心して送るために支援を受けたい
このように、相談支援専門員は担当する年代や分野によってサポート内容が異なり、利用者やご家族の状況に応じて柔軟に対応しています。
主な業務内容
相談支援専門員の業務は幅広いですが、ここでは代表的な流れと、実際の現場でよくある相談事例を紹介します。
1. 相談受付・ヒアリング
最初は、利用者やご家族からの相談を受けます。
例1【成人の精神障害の場合】
高校卒業後しばらく無職で実家暮らしをしていた方から、「自分も今の生活を抜け出すために働きたいが、何から始めたらいいか分からない」と相談を受けたケース。
相談支援専門員は、本人の希望や生活状況を丁寧に聞き取り、「就労移行支援事業所」などを紹介し、ステップを踏みながら社会参加をサポートします。
例2【障害児の場合】
3歳健診で発達の遅れを指摘され、今後の療育や学校生活に不安を感じているご家庭から相談を受けたケース。
相談支援専門員は、ご家族と一緒に今の悩みを整理し、必要に応じて療育機関につなげる役割を担います。
2. サービス等利用計画書の作成
ヒアリングした内容をもとに、「サービス等利用計画書(ケアプラン)」を作成します。
これは「どんなサービスを、どのくらいの頻度・期間で利用するか」を明確にした計画書です。たとえば「週に3回、就労移行支援を利用」「毎週月曜日と金曜日に放課後等デイサービスを利用」など、本人・ご家族の希望や課題に合わせて具体的に提案します。
3. 関係機関との調整・連絡
計画ができた後は、市役所(行政)、サービス事業所、医療機関、学校などさまざまな関係機関と連携しながら、支援がスムーズに進むよう調整します。たとえば、就労支援と医療の両立、学校と福祉サービスの利用日程調整など、状況に合わせて幅広く対応します。
この関係機関同士をつなぐのも相談支援専門員の大切な役割であり、関係機関との日程調整や電話連絡が多いのも特徴です。
4. モニタリング(定期的な見守り・状況確認)
サービス利用が始まった後も、定期的に面談や訪問を行い、サービス内容が本人に合っているか・新たな困りごとが出ていないかを確認します。状況が変わった場合は計画を見直したり、新しい支援を提案したりすることもあります。
5. 記録・書類作成
日々の相談内容や支援経過はきちんと記録・管理し、必要に応じて行政やサービス事業所への報告書を作成します。
相談支援専門員の報酬体系としては、国からの給付になるため、利用者からお金を直接いただくことは基本的にありません。サービスを作り、それを国に送付請求することで始めて報酬を得られることが出来ます。
相談支援専門員の一日の流れ
ここでは、現場で働く相談支援専門員の一日の例をザックリとご紹介します。
訪問が立て込んだ一日(外出中心)
- 午前中
- 自宅から直接利用者宅に伺いモニタリング実施
- そのまま次の利用者宅へ直接訪問して、計画案を確認してもらう
- 昼〜午後
- 出先で空いた時間にランチを取る
- 車で午前中の2件の記録をパソコンで行う
- 空いた時間で明日以降の担当者会議のための関係機関との調整を行う
- 夕方
- 事務所にいったん戻り、終わらなかった分の記録をまとめる
- 明日以降の予定を再度確認して退勤
訪問が少ない一日の流れ(事務・調整業務中心)
- 午前中
- 事務所に出勤し、メール・電話で利用者やご家族、関係機関からの問い合わせに対応
- 新規相談の電話を受け、アセスメントの事前準備や必要書類の確認
- 計画書の修正依頼や市役所への提出書類をまとめる
- 昼〜午後
- 事務所で同僚と情報共有やケース検討ミーティング
- パソコンで複数利用者のモニタリング記録やサービス等利用計画書を作成
- 明日以降の訪問や会議に向けて、関係事業所・医療機関と電話やメールで日程調整
- 夕方
- 当日中に処理する必要がある記録や報告書を最終チェック
- 1件だけ緊急の家庭訪問が入り、短時間だけ外出
- 事務所に戻って明日の予定確認と必要書類の準備をし退勤
外出(訪問)と事務作業(調整や書類)がバランスよくあるのが特徴です。
夜勤は基本的になく、働き方の調整もしやすい職場が多いです。
どんな人がなれる?資格・研修について
相談支援専門員になるためには、一定の資格や実務経験、研修の受講が必要です。
資格・研修ルート
- 主流は社会福祉士・精神保健福祉士などの国家資格ルート
- 多くの相談支援専門員は社会福祉士や精神保健福祉士、介護福祉士など福祉分野の資格や経験を持っています。
- 看護師ルートは少数派だが強みもあり
- 看護師資格で相談支援専門員になる方もいますが、現場ではまだ多くありません。ただし、医療的な知識や経験は利用者の健康や医療的ケアが必要な場合などに強みになります。
- 研修について
- 相談支援専門員は、「相談支援従事者初任者研修」を受講し修了することが必須です。
- ケアマネのような国家試験はありませんが、研修を受けるには一定の実務経験や資格要件があります。
- さらに、5年ごとに「現任研修」という更新研修を受ける必要があります。
- 無資格経験ルート
- 無資格でも経験と上記研修を受けることで資格を得ることもできる

まとめ
相談支援専門員は、障がいのある方やそのご家族が地域で安心して暮らすために、必要なサービスや支援を一緒に考え、つなぎ、支える伴走者です。
イメージとしては「障がい者分野のケアマネ」と考えていただいておおむね間違いありません。利用者・ご家族だけでなく、行政や福祉・医療・教育など多方面と連携する幅広い仕事です。
今後、「具体的な資格取得の流れ」「現場のリアルな働き方」「将来性やキャリアパス」「利用者・家族の声」「相談支援専門員に向いている人」などを個別記事として順次追加予定です。
気になるテーマがある方は、今後の記事もぜひご覧ください。


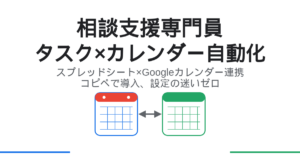


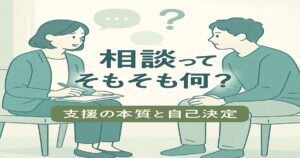


コメント