「相談支援専門員」として働いていると、日々多様な相談に向き合うことになります。一見相談というと、悩みごとを持つ人が専門家に助けを求めてくる、専門家が正解を出す、そんなイメージを持たれがちです。しかし現場に立っていると、本当の意味での相談や支援はそんなに単純なものではないと感じることが多々あります。
答えがないから悩む。「一緒に考える」相談のかたち
利用者さんやご家族から「○○の事業所ってどうですか?」と尋ねられることはよくあります。今までかかわったことがあり、スタッフの人となりを知っている事業所であればいいのですが、毎回そうとは限りません。福祉業界も人も看護介護ほどではないですが、人の入れ替わりがある程度ある業界でもあるため、電話をしたら管理者が変わっていたということもあります。
特に新しく担当になった地域やサービス分野では、自分自身が直接関わったことのない事業所や新設の事業所も多く、その場ですぐに答えを出せないという経験を何度もしてきました。
たとえば、ある利用者さんから「今度見学に行こうと思っている事業所があるんですが、実際どうなんでしょう?」と聞かれたことがあります。その時点で私に分かっていたのは、パンフレットに書かれているサービス内容や、他の支援者から間接的に聞いた評判くらいでした。本当の雰囲気や、日々の細かな対応は実際に行ってみなければ分かりません。
こうしたときには、まず「自分が何を一番大事にしたいのか」「どういうことが気になるのか」を一緒に整理していきます。
たとえば、通いやすさや送迎の有無、スタッフの雰囲気、提供される活動の内容、利用者層の年齢や性格、医療的ケアへの対応の有無など、本人や家族によってこだわるポイントはさまざまです。
この時、「他の人が良いと言っているから良い」「ネットの口コミが高いから安心」といった他者基準だけでなく、
「自分にとって何が一番大事か?」という観点を一緒に探すことが大切だと感じています。
実際、見学の際も「何を見たらいいか分からない」「聞きたいことが思い浮かばない」という方も多いので、
「例えばこういう点をチェックしてみては?」と具体的にアドバイスしながら、一緒に情報を集めていきます。
また、他の利用者さんの体験談や、同じ悩みを持っていた方の声を参考にすることもあります。事業所ごとに得意・不得意な領域や特色があり、たとえば「アットホームな雰囲気が売り」「医療的ケアに強い」「レクリエーションの幅が広い」など、それぞれ個性が異なります。
私たち支援者自身も、「もし自分がこの人の立場だったらどこを大切にするだろう」と自問自答しながら、現実的な選択肢を一緒に探っていきます。このような内なる対話も、支援の現場では欠かせない要素です。
情報が足りないときにどうするか
相談支援をしていると、すぐに十分な情報が集まらないこともよくあります。
そんなときは無理に「分かったふり」をせず、「現時点で分かっている範囲」を正直に伝えます。
そのうえで、必要なら一緒に見学へ行く、関係者や他の利用者の声を新たに集めてみる、担当者に直接問い合わせてみるなど、利用者さんと二人三脚で確かめていくプロセスを大事にします。
この過程で、利用者さん自身が「思ったより気にしない部分があった」「やっぱりスタッフとの相性が一番気になる」など、新たな発見が出てくることもあります。
一緒に迷いや不安を言葉にして、選択肢を一つずつ現実的に絞り込んでいく、その対話の時間こそが「相談」の本質だと思います。
相談支援は「納得できる選択」を支えること
支援職の仕事は、悩みをゼロにしたり、すぐに答えを出したりすることではありません。
利用者さん本人や家族が、「自分たちで選んだ」と思える経験を一つでも多く重ねること、そのために必要な情報や選択肢を共に集め、「今できる範囲のベストな判断」を一緒に考えていくことだと思います。
実際には、制度の制約や予算、待機人数、地域の事情など、思い通りにならない現実にも直面します。それでも、本人や家族が「今回はここが一番納得できる」と感じられる選択になるように、できるだけ丁寧に寄り添い続けたいと思っています。
支援者として全ての情報や最適解を持っているわけではありません。大事なのは、分からないことや不安を一緒に受け止め、対話を積み重ねていく姿勢です。
ときには「このエリアで初めてのケース」「今までにないニーズ」など、誰も正解を持っていない場面もあります。
そんな時は「一緒に調べてみましょう」「他の事業所もあたってみます」と率直に伝え、新しい情報を少しずつ広げながら利用者さんと歩調を合わせて進んでいくことが何より大切です。
一方的に情報や指示を押し付けるのではなく、利用者さん自身が「自分の選択肢を自分の言葉で語れる」ように後押しをする。その積み重ねこそが、信頼関係の土台になると感じています。
支援の現場で心がけていること
現場で意識しているのは、
- 一度に完璧な答えを出そうとしすぎないこと
- 分からないことを素直に伝え、「一緒に調べる」「一緒に考える」姿勢を持つこと
- 利用者さんやご家族の本音に気づけるよう、小さな違和感や表情の変化にも耳を傾けること
また、事業所の見学時や担当者とのやり取りの中で、その場の雰囲気や言葉遣い、スタッフの対応など、パンフレットには載らない空気を一緒に感じることも意識しています。
「ここなら安心できそう」「ここはちょっと違和感があるかも」といった感覚も、相談の過程で大事なヒントになっています。
まとめ
相談支援専門員の仕事は、正解を知っている人や専門的な指示を出す人ではなく、利用者さんやご家族とともに“納得できる選択”を探し続ける存在だと思います。
分からないことや不安、迷い――そうしたものも、利用者さんと一緒に受け止め、対話を重ねながら一歩ずつ進んでいく。そのプロセスこそが、相談支援の本当の価値であり、この仕事のやりがいだと感じています。
今回の記事は少し抽象的な話が多くなりましたが、実際の現場でも「形のない悩み」や「正解のない問い」に向き合う時間が多いものです。文章にすることで、普段はあまり意識していなかった自分自身の考えや迷いにも、改めて気づくことができました。
日々の現場のなかで、思い通りにいかないことや答えが見つからない場面はたくさんあります。それでも利用者さんと一緒に考え続ける姿勢だけは大切に、これからも支援の現場と向き合っていきたいと思います。
もしこの記事を読んで、少しでも共感する部分があればうれしいです。
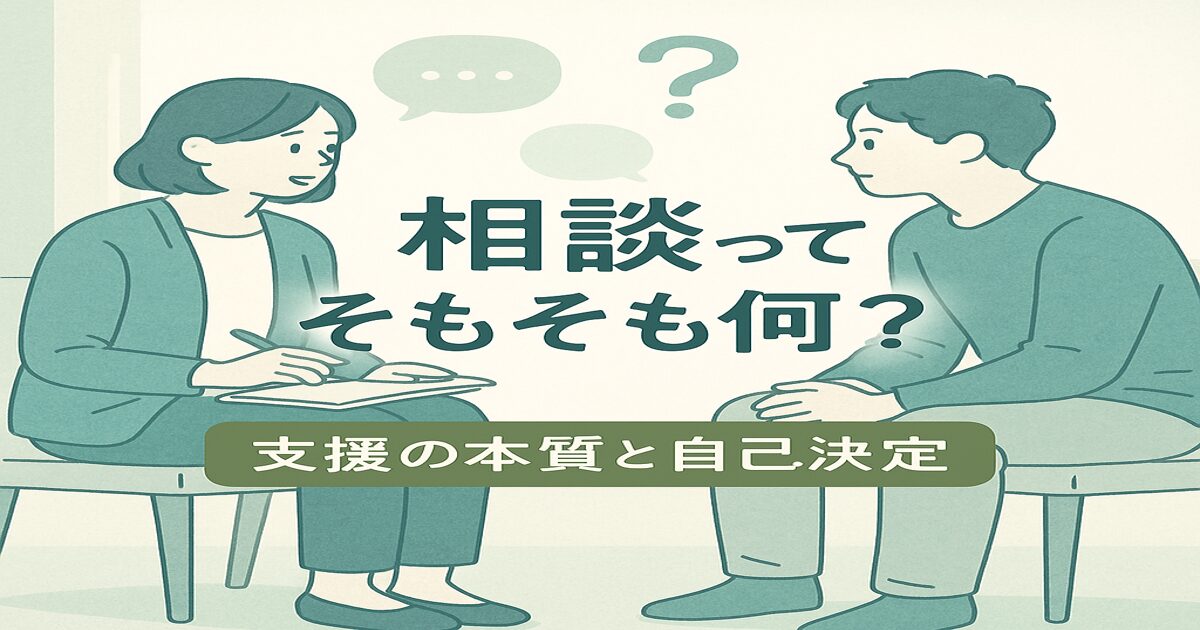

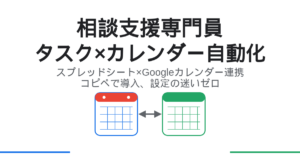





コメント