私の投資ヒストリー
私自身のこれまでの投資遍歴と現在の投資スタイル、今後の方針について備忘録も兼ねて記録していきます。
正確な年号は覚えていないので大体です。
現在お金や投資の知識は今やどこでも簡単に手に入る時代です。このブログでも、資産運用に関する細かい用語や仕組みの解説は必要最小限にとどめています。もし分からないことがあれば、その都度ご自身で調べてみてください。
ただ、看護師として働いてきた私が強く感じるのは、「看護師こそお金の勉強が必要」ということです。夜勤もあって初任給は比較的高めですが、その後の昇給ペースは決して速くありません。体力が求められる仕事だからこそ、早めに投資を始めて資産運用を考えることが大切だと思っています。
このブログが、同じような看護師の方や、これから資産運用を考えている方の背中を少しでも押せたら嬉しいです。
実際にやってみると、投資は思っているほど難しいものではありません。
時系列
- 2018年秋~冬ごろ
- YouTube(両学長)の動画で投資を知る
- 旧NISAでVTIを毎月上限まで積み立てする
- 2019年春~夏ごろ
- 余剰資金ができ、特定口座でS&P500とオールカントリー(全世界株式)にも投資開始
- さらに分散目的で何となく日本国債インデックスファンドにも特定口座で積み立て開始
- 2019年冬~2020年春ごろ
- 半年ほど日本国債インデックスファンドに投資したが若い段階ではもっとリスク取れるし「これ意味ないな」と思い売却
- 積み立てNISA開始から(たぶん)1年後くらい、ネオモバイル証券で日本の高配当株(KDDI、三井住友UFJなど)の購入を開始
- 同じ頃に米国高配当ETF(SPYD、HDV)にも投資開始
- 上記どちらもまたまたYouTube(両学長)の影響
- 2020年春~2023年春ごろ
- 積み立てNISA、ETF、日本高配当株を定期的に買い増し
- 資金的に厳しくなったので、どこかのタイミングでETFの積み立ては中止
- どこかのタイミングで、特定口座のオールカントリーの分のお金をS&P500に回した
- 2023年春~冬ごろ
- ネオモバイル証券サービス終了に伴い、日本株高配当株をSBI証券へ順次移管
- 資金的に厳しくなったので、どこかのタイミングで特定口座のS&P500は積み立て中止
- 2024年1月
- SBI証券の新NISAに切り替え、オールカントリー1本に絞って積み立て継続
- 楽天証券のNISA、特定口座売却せずにそのまま運用中
- ETFは理由忘れたが現金が必要となり売却した(2023年度中だったかも?)
- 日本の高配当株も引き続き投資中
- 2024年夏ごろ
- 現金が必要になり、特定口座のS&P500・オールカントリーを売却し現金化
- 継続して積み立て購入しているのは新NISAと高配当株のみ
- 2025年7月現在
- 積み立てNISAは継続中
- 高配当株は資金に余裕がなく停止中
投資初期――「両学長」との出会いと長期積立スタート
投資を始めたのは、YouTubeで両学長の動画を偶然観たのがきっかけです。
当時はまだ現金にも余裕があり、「このまま預金だけではお金は増えないし、若い今なら多少失敗してもやり直せる」と思い、投資を始めることにしました。長期・積み立て・分散を意識し、まずは積み立てNISAでインデックス投資からスタート。
正直、やり始めてみると一度設定するだけであとは何もやることがなく、「こんなもんか?」という肩透かし感もありました。
FXやデイトレードにも少しは興味がありましたが、「お金を減らしたくない」という気持ちが強く、一度も手を出していません。
今思い返しても、最初に投資の入り口をつくってくれた両学長にはとても感謝しています。いろいろ言われることも多い方ですが、「ネット上で投資のハードルを下げてくれた功績」は本当に大きいと感じています。今はもう動画は見ていませんが、きっかけをもらえたことには感謝しています。
投資中期――「高配当株」へのシフトと家族の納得感
その後、投資にも少しずつ慣れてきて、インデックス投資だけでは「やることがない」「増えている実感が乏しい」と感じるようになりました。
ただ、細かく企業分析をしたり、日々の株価に一喜一憂したりするタイプではない自覚もあったので、何か自分でも続けやすいスタイルがないかと模索していました。
そこでまた両学長の動画で紹介されていた「高配当株投資」に興味を持ちます。最初に銘柄選定の基準をしっかり決めて、一度買ったら基本的には売らない。配当金や優待を受け取りながら、あとはほったらかし。これなら自分にも合いそうだと思い、実際に日本の高配当株や米国の高配当ETFに投資を広げていきました。
この「配当金が入る」「優待でもらえるクオカードや食品が届く」という体験は、投資への納得感をパートナーと共有するうえでも大きなメリットになりました。
コロナ前から続けてきたインデックス投資は含み益がかなり出ていましたが、実際に利益を確定しない限り「実感が湧かない」部分も多く、当初はパートナーも投資に対して半信半疑でした。でも、高配当株や優待で“目に見える成果”が届くと、パートナーも自然と投資の良さを認めてくれるようになりました。
投資後期――家族の変化と資産配分の見直し
これまではパートナーと二人暮らしだったので、毎月の家計にも余裕があり、現金比率が10%を切るくらいまでフルで投資に回していました。
しかし、子どもが生まれてからは家計のバランスも大きく変化しました。大きな車の購入や住宅の取得、そして転職による収入の変化――。
看護師から特養、さらに相談支援専門員へとキャリアを変えてきたことで、今は以前より給料も下がっています。そのため、高配当株の買い増しはストップしていますが、積み立てNISAと保有中の高配当株投資だけは継続しています。
家族が増えることで必要な現金も増え、以前のような“フルインベスト”はできなくなりましたが、「生活と投資の両立」「無理のない範囲での資産運用」が今の自分にはしっくりきています。
まとめ
投資は難しく考えがちですが、実際にやってみると「一度設定してあとは待つだけ」という部分が多く、想像よりずっと手間はかかりません。
このブログでは、細かい投資理論の解説よりも「自分の経験やつまずき」「家計や家族の変化とどう向き合ってきたか」を中心に、これからもリアルな記録を続けていきます。
看護師という職業柄、若いときから収入が高めな一方で、その後の伸びしろや体力の問題には早めに向き合う必要があると実感しています。
「少しでも早く」「自分に合った形」で資産運用を始めてみてほしい――このブログがそのきっかけになれば嬉しいです。
高配当株については、一応それっぽい基準も作っているので、またどこかの機会で公開します。
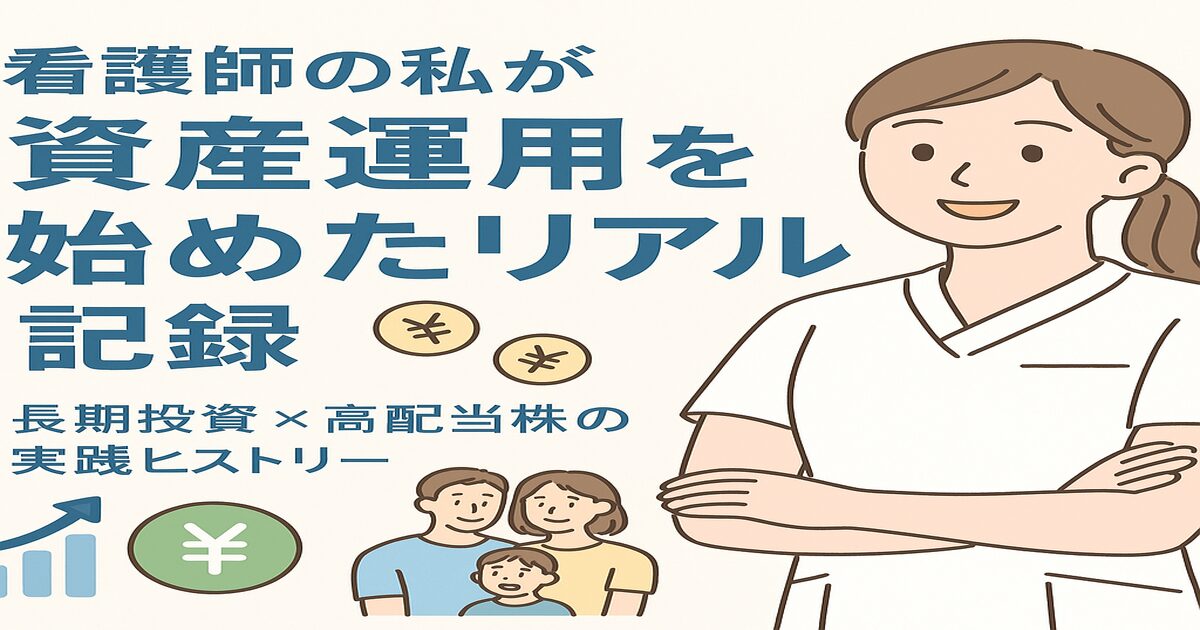

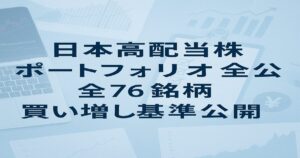
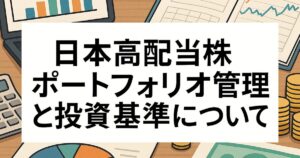
コメント